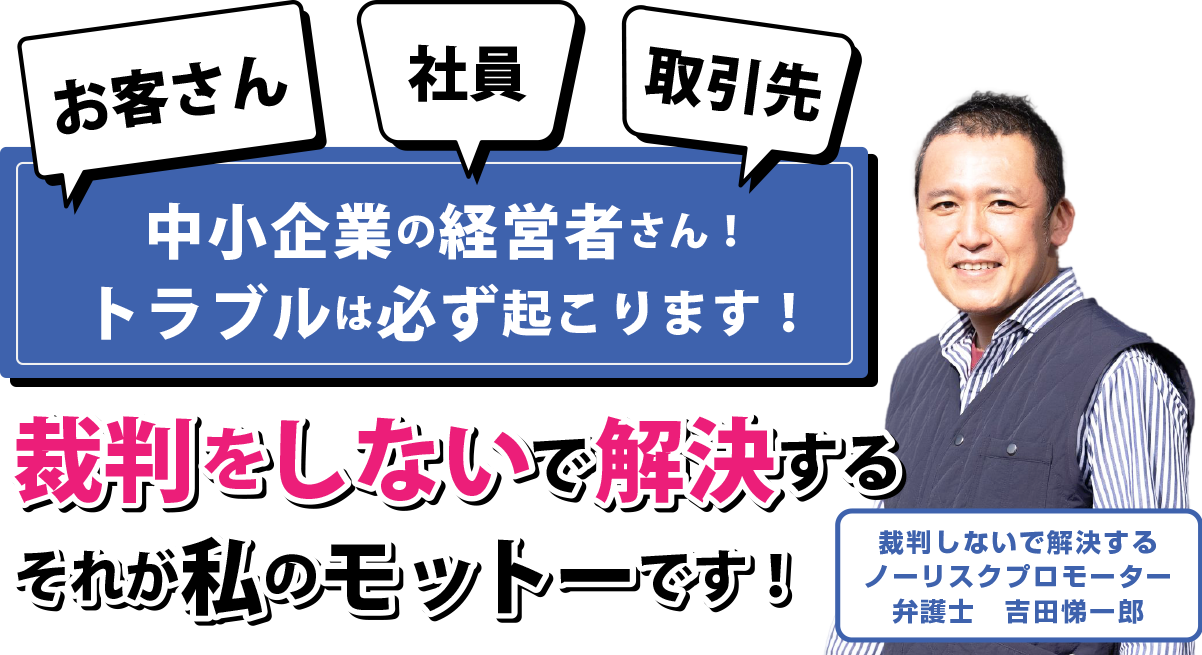
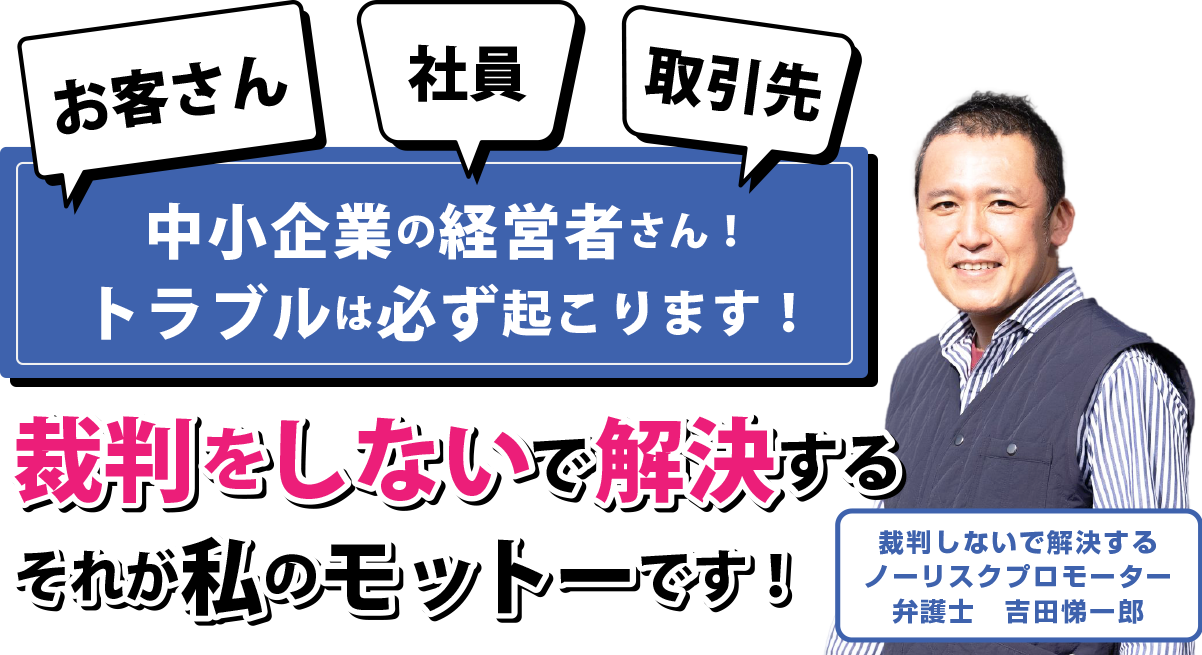
「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
初めての方はこちらのオススメ記事をお読みください一覧はこちら
退職直前にメール180通削除? 業務上のメールは誰のもの?
社員が退職直前に
自分の業務メールを一斉に削除して退職。
会社の業務上のメールは誰のものか?
社員に削除する権限はあるのか?
今回はこの辺のことを
深掘りしてみたいと思います。
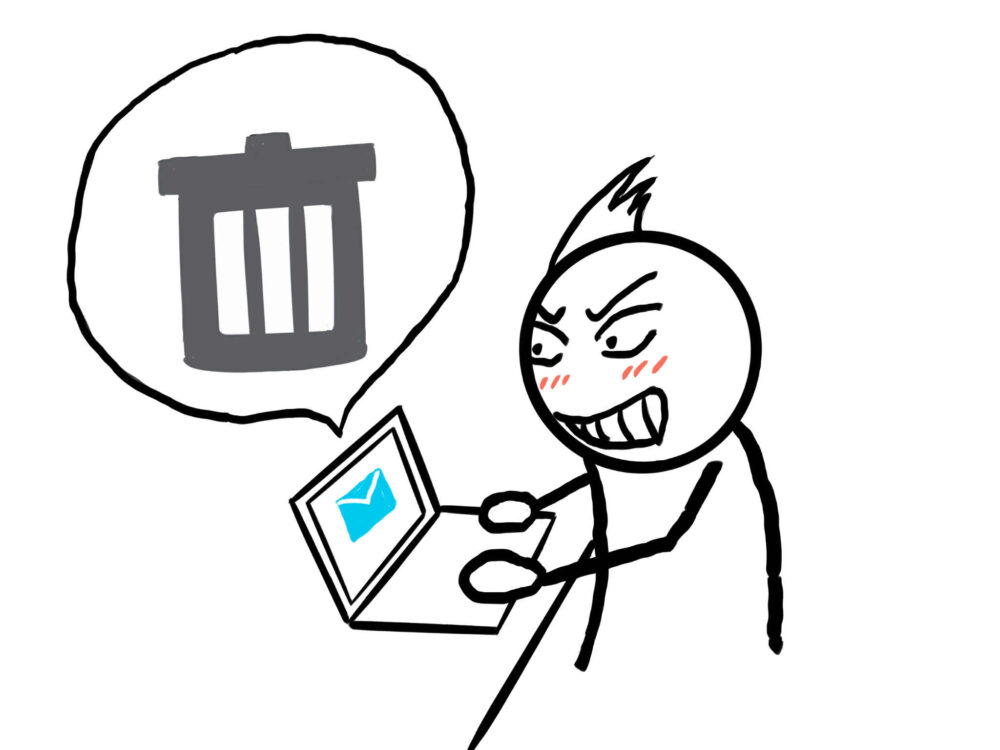
(今日の「棒人間」 メールを削除する??)
<毎日更新1627日目>
退職直前にメール180通を削除??
ある会社の社員が
退職直前の3日間に
自身が使用していた会社の業務上のメール
約180通を削除して退職しました。
会社は
この社員が会社に対する業務妨害をはかり
営業秘密を社外に持ち出した疑いがあると考え
メールの削除行為は不法行為であるとして
退職した社員に対して損害賠償請求の
裁判を起こしました。
これに対し
この社員は
メールの保存ないし削除は
そのメールを受送信した個人の裁量に
委ねられていたなどと反論しました。
この裁判で判決は
メールは、退職者個人の私信ではなく、会社に帰属すべき情報財産
であると判断しました。
その上で
退職者が退職に先立ち、メールを意図的かつ一斉に削除したことは、会社の財産権を侵害し、会社の業務を妨害するものであり、不法行為に該当する
と判断し
この社員に対して200万円超の
損害賠償を命じました。
ちょっとおもしろい事件なので
今回はこの問題を深掘り
してみたいと思います。
業務上のメールは誰のもの?
この問題は
そもそも
会社の業務上のメールは誰のものなのか?
というのがその出発点です。
というのは
確かに会社の業務上のメールは
形式上は会社のドメインを使った
「業務連絡ツール」ではあります。
しかし
同時に
業務上のやり取りの中に個人的な
挨拶・雑談・感情表現などが
混じることがあります。
そして
実際のメールの受送信や削除なども
多くの場合社内の明確なルールはなく
実際上は使用する「本人に任せる」という
運用が定着していることが多いでしょう。
つまり
会社の業務上のメールというものは
「ビジネス文書」でありながら
私信的な性格を帯びやすい媒体
と言えるわけです。
しかし
会社の立場からすれば
会社の業務時間中に
会社の設備を用いて
会社の業務目的で作成されるメールですから
これは当然会社の所有物である
という認識になります。
また
業務上のメールは
時に会社の重要な営業秘密や情報資産
としての性質も持っています。
上記の裁判の判決でも
取引先との発注書や見積書等の資料のみでは、そのような発注ないし見積もりになった経緯を理解することができず、メール内容を検討することは必要であるし、すでに取引関係が終了した取引先とのメールであっても、将来的な取引再開の可能性や過去の取引に関するクレーム等があった場合の対応の必要性があり、当然に不要になるものではない。
と指摘されています。
それゆえ
業務上のメールは社員個人の「私信」ではなく
会社に帰属すべき「情報財産」である
と判断されているわけです。
業務上メールをめぐるトラブルを予防するには?
それにしても
メールを180通も削除するのは
それだけで大変な作業ではありますが
退職直前のこうした行為は
やはり業務妨害や何かを隠蔽する
意図を感じてしまいますね。
上記のとおり
業務上のメールの「私信的な性格」ゆえに
それが会社のものなのか
個人の裁量にゆだねられたものなのかが曖昧で
ときにそれがトラブルのタネに
なったりもするわけです。
それでは
こうしたトラブルを「予防」するためには
どうしたら良いのでしょうか?
上記の裁判でも
社員側は
メールの保存ないし削除は、そのメールを受送信した個人の裁量に委ねられていた
と主張しているところが
1つのポイントです。
そして
この点は判決においても
社内においてメールの削除に関するルールが存在しないのは、個人の裁量による削除が想定されていないからにすぎないというべきである
と指摘しています。
すなわち
たとえば就業規則や社内規定
(情報セキュリティポリシー
IT機器使用規程等)において
業務上のメールの保存や削除
についてのルールを明文化し
それを社員に周知させることです。
具体的には
などと定めておくことです。
その上で
たとえばメールの削除はシステム管理者
のみ可能であるとするなど
削除権限を明確にしておくことです。
さらに
技術面でのデータ保全の
体制を作っておくこと。
具体的には
クラウドメールの管理者設定で
自動バックアップを有効化しておくとか
各ユーザーの削除操作があっても
一定期間は復元可能にするなど
万が一削除されてもメールを保全できる
体制を整備することです。
その「私信的性格」ゆえ、会社のものか
個人の裁量かが曖昧な面がある
会社の業務上のメール。
今後もこうしたトラブルは
増えるものと予想されます。
会社としても
こうしたトラブルを予防するための対策は
きちんとやっておきたいものです。
それでは
また。
◼️新作note(有料記事)「ファン付き作業着は義務?」知らなきゃ大損!夏の熱中症対策、会社がすべきこと
◾️裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール
◾️あなたの会社のトラブルを予防します〜あんしん法務ガード(顧問契約)
◼️「裁判沙汰」を予防する、契約書作成・リーガルチェックサービス
◾️【無料】セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付
◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)
最新動画
今回は、「「LINEパワハラ」で訴えられる!?中小企業が今すぐ見直すべき社内ルール」というテーマでお話ししています。
活動ダイジェスト
お問い合わせ

| 住所 | 150-0031 東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階 マップを見る |
|---|---|
| 受付時間 | 【平日】9:30〜18:00 【土曜日】9:30〜12:00 |
関連記事
カテゴリー
- キャンプ (5)
- このブログのコンセプト (23)
- セミナーのお知らせ (3)
- フリーランス保護法 (3)
- 一般的な法律相談 (352)
- クレーマー・カスハラ対策 (48)
- ネットのトラブル (6)
- フリーランスの法律相談 (3)
- 下請法 (28)
- 不正競争防止法 (8)
- 事業承継問題 (14)
- 企業損害のトラブル (4)
- 会社法関係 (37)
- 個人情報保護法 (2)
- 倒産・債務整理 (2)
- 債権回収 (10)
- 内容証明 (3)
- 内部通報(公益通報) (3)
- 刑事関係 (4)
- 名誉・プライバシー・肖像権侵害 (2)
- 契約書 (39)
- 悪徳業者とのトラブル (6)
- 損害賠償 (3)
- 景品表示法 (11)
- 株主総会トラブル (10)
- 業務委託契約 (11)
- 法律相談を受ける (9)
- 独占禁止法 (4)
- 環境問題 (2)
- 知的財産権 (14)
- 税金関係 (5)
- 行政処分 (1)
- 裁判 (33)
- 証拠を集める (5)
- 遺産相続・遺言問題 (4)
- 顧客とのトラブル (13)
- 不動産に関するトラブル (2)
- 不動産業の法律相談 (67)
- 介護業界のトラブル (1)
- 仕事術・時間術 (67)
- 健康・セルフケア (26)
- 勉強法 (5)
- 営業 (3)
- 子育て (9)
- 建設業の法律相談 (321)
- 会社の株式のトラブル (1)
- 元請けや下請けのトラブル (10)
- 取引先とのトラブル (50)
- 契約書のトラブル (3)
- 社員との労働トラブル (252)
- 弁護士業界 (41)
- 情報発信 (133)
- SNS (3)
- Voicy(音声配信) (2)
- YouTube (9)
- セルフマガジン (1)
- ブログ (88)
- メルマガ (4)
- 棒人間 (3)
- 電子書籍(Kindleブック) (1)
- 料理 (2)
- 最近読んだ本 (20)
- 生き方 (55)
- 私(吉田悌一郎)ってどんな人? (32)
- 私の弁護士としてのスタンス (14)
- 酒こそわが人生 (19)
- 離島での弁護士活動 (4)
- 顧問契約 (23)
人気記事(トータル)
人気記事(月間)
月別記事
- 2026年1月 (20)
- 2025年12月 (31)
- 2025年11月 (30)
- 2025年10月 (31)
- 2025年9月 (30)
- 2025年8月 (31)
- 2025年7月 (31)
- 2025年6月 (30)
- 2025年5月 (31)
- 2025年4月 (30)
- 2025年3月 (31)
- 2025年2月 (28)
- 2025年1月 (33)
- 2024年12月 (31)
- 2024年11月 (30)
- 2024年10月 (31)
- 2024年9月 (30)
- 2024年8月 (31)
- 2024年7月 (31)
- 2024年6月 (30)
- 2024年5月 (31)
- 2024年4月 (30)
- 2024年3月 (31)
- 2024年2月 (29)
- 2024年1月 (31)
- 2023年12月 (31)
- 2023年11月 (30)
- 2023年10月 (31)
- 2023年9月 (30)
- 2023年8月 (31)
- 2023年7月 (31)
- 2023年6月 (30)
- 2023年5月 (31)
- 2023年4月 (30)
- 2023年3月 (31)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (31)
- 2022年12月 (31)
- 2022年11月 (31)
- 2022年10月 (39)
- 2022年9月 (4)
- 2022年1月 (1)

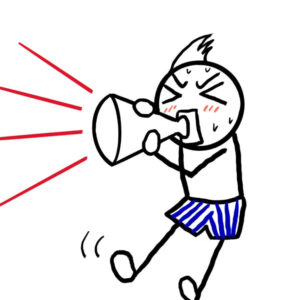

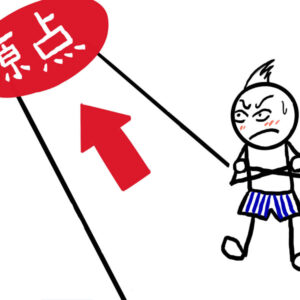
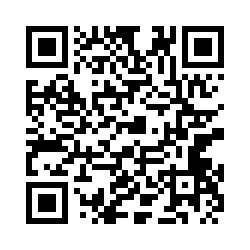













Profile
中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。