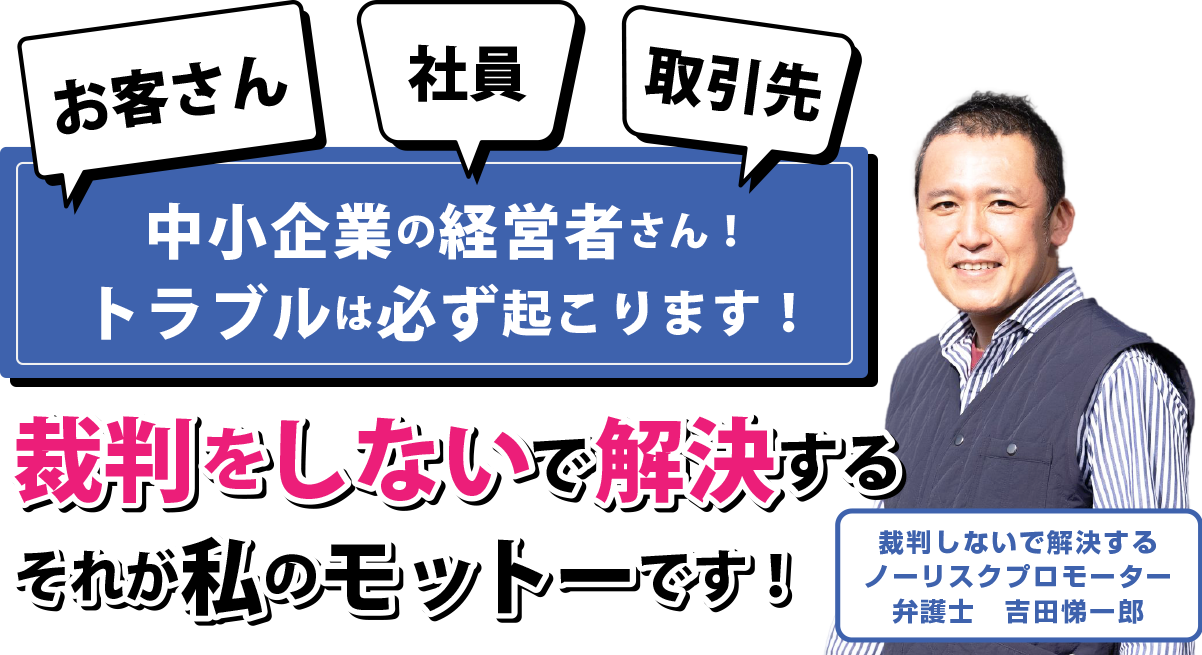
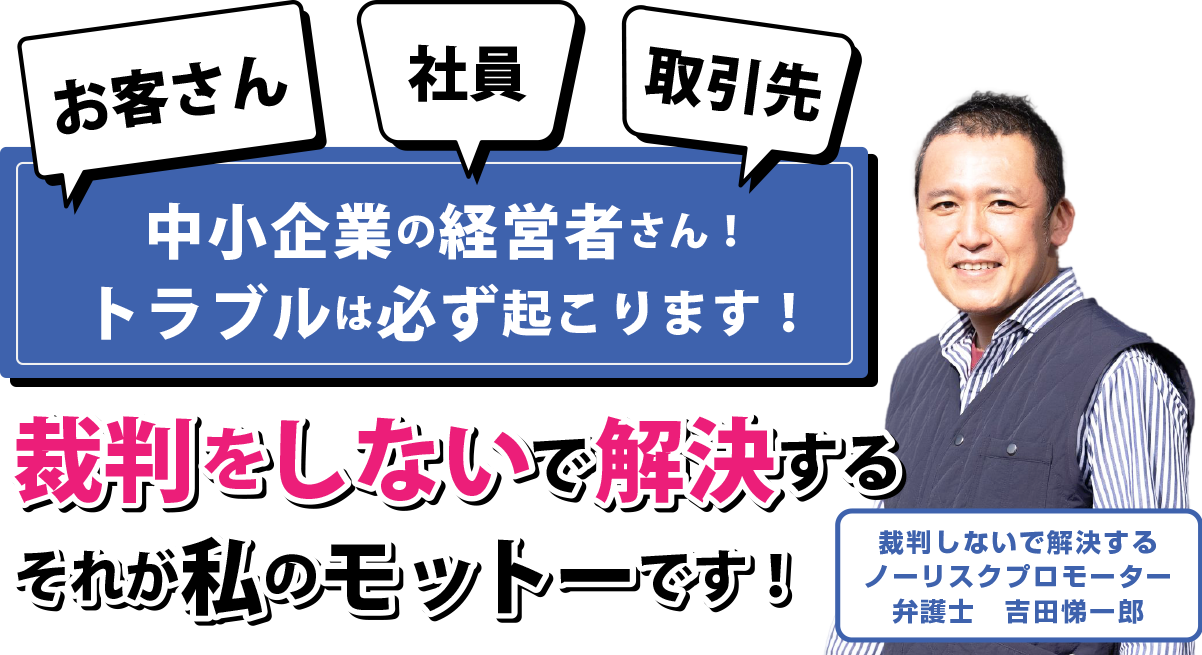
「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
初めての方はこちらのオススメ記事をお読みください一覧はこちら
「解雇は最終手段」・・・でも限界? 裁判で負けた企業の実例から学ぶ
社内でいろいろと問題を起こす社員に
会社を辞めてもらいたい。
しかし
日本の法律上「解雇」は
簡単ではありません。
今回は
実際にあった解雇事例から
学んでみたいと思います。
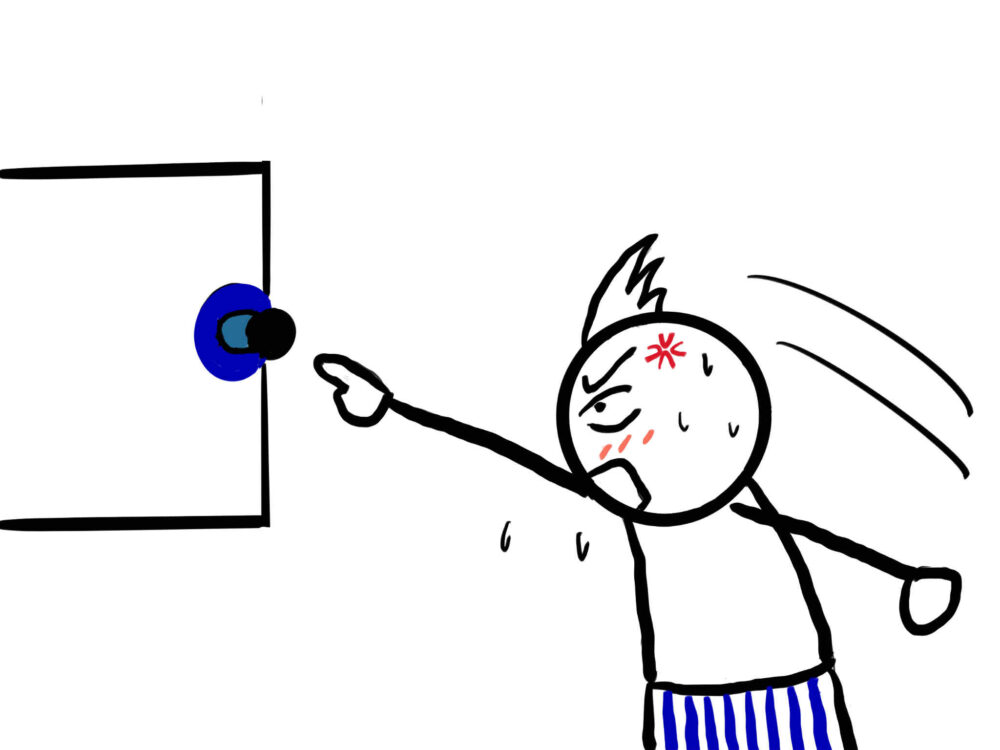
(今日の「棒人間」 最終兵器??)
<毎日更新1616日目>
「論破系」新人に手を焼く会社
人手不足の今の世の中
新たに入社してくれる若手社員は貴重です。
しかし
当たり前ですが
誰でもいい
というわけには行きません。
東京都心に本社を構える
老舗メーカー会社での出来事。
ある困った新人社員が入社しました。
この社員は
入社前の内定式に欠席
内定者懇談会もアルバイトを理由に欠席。
入社前説明会では
ボサボサの髪の毛で出社し
自己紹介では制限時間をオーバーして
日本の年金制度についての持論を
勝手に展開して注意を受けました。
工場の研修にもだらしない服装で出社し
作業がうまくいかずに大声を出して
工具を放り投げるなどの問題行動も。
研修のときも
などと反発していたそうです。
その後
営業部門に配属されたこの社員。
作成した書類について
先輩社員が質問すると
と投げやりに返答したそうです。
3ヶ月の試用期間が過ぎようとするとき
上司はこの社員に退職を勧めました。
そして
退職に応じるなら1カ月は
働かずに就職活動をしていいと提案。
しかし
この社員は「辞めるつもりはないです」
とこの提案を拒否。
会社は
6月末までだった試用期間を1ヶ月延長し
会議室にこの社員の席を設けて
特に仕事は与えませんでした。
それでも「解雇」は無効??
7月下旬に行われた面談で
この社員の上司や役員から
といった言葉が飛び出しました。
しかし
この社員はそれでも退職を
拒否し続けました。
会社は試用期間をさらに1ヶ月延長
その上で8月末に解雇予告通知書を交付し
9月末で解雇しました。
この社員は
「不当解雇」であると主張し
法廷闘争に発展。
裁判所の判決は
「新人男性の勤務態度などに少なくない
問題があった」などとしつつも
解雇権の濫用であるとして
会社が行った解雇は無効である
と判断しました。
「解雇」するための高いハードル
法的に社員を解雇するためには
② 解雇の社会通念上の相当性
という2つの要件が必要です。
この2つの要件を満たさない解雇は
解雇権の濫用として法的に
無効となります。
実際には
この2つの要件を満たすことは
容易ではありません。
上記の事例では
裁判所は
研修時点でこの社員の問題が
報告されていたにもかかわらず
この社員に対して直接の指導が
なされなかったことなどを
指摘しています。
さらに
この社員に対して
会議室に席を設けて特に
仕事を与えない「追い出し部屋」
の待遇を行ったことなども問題視。
その辺の事情から
解雇は無効であると判断したようです。
このように
日本の裁判所は
解雇を非常に厳しく判断します。
解雇は
あらゆる手段を尽くした後の
本当に最後の手段という位置付けでしょう。
また
解雇に至るまでのプロセスも
非常に重視されます。
安易な解雇は
後々「不当解雇」の裁判を
起こされるリスクは高いので
注意すべきです。
さて
今回の事例では
会社がこの社員の「試用期間」を
延長していることも論点となっています。
果たして
会社が決まった「試用期間」を
延長することができるのか?
長くなりましたので
この辺はまた明日お話しします。
それでは
また。
*なお、上記事例は、日本経済新聞「揺れた天秤」シリーズから引用しました。
見限られた「論破系」新人 解雇無効訴訟 「研修、強制できないですよね?」 「追い出し部屋」は妥当か
◼️新作note(有料記事)「ファン付き作業着は義務?」知らなきゃ大損!夏の熱中症対策、会社がすべきこと
◾️裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール
◾️あなたの会社のトラブルを予防します〜あんしん法務ガード(顧問契約)
◼️「裁判沙汰」を予防する、契約書作成・リーガルチェックサービス
◾️【無料】セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付
◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)
最新動画
今回は「カンタンに作れる? おつまみ3選」というテーマでお話ししています。
活動ダイジェスト
お問い合わせ

| 住所 | 150-0031 東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階 マップを見る |
|---|---|
| 受付時間 | 【平日】9:30〜18:00 【土曜日】9:30〜12:00 |
関連記事
カテゴリー
- キャンプ (5)
- このブログのコンセプト (23)
- セミナーのお知らせ (3)
- フリーランス保護法 (3)
- 一般的な法律相談 (363)
- AIと法律問題 (3)
- クレーマー・カスハラ対策 (48)
- ネットのトラブル (6)
- フリーランスの法律相談 (3)
- 下請法 (28)
- 不正競争防止法 (8)
- 事業承継問題 (16)
- 企業損害のトラブル (4)
- 会社法関係 (37)
- 個人情報保護法 (2)
- 倒産・債務整理 (2)
- 債権回収 (10)
- 内容証明 (3)
- 内部通報(公益通報) (3)
- 刑事関係 (4)
- 名誉・プライバシー・肖像権侵害 (2)
- 契約書 (42)
- 悪徳業者とのトラブル (7)
- 損害賠償 (3)
- 景品表示法 (11)
- 株主総会トラブル (10)
- 業務委託契約 (11)
- 法律相談を受ける (9)
- 独占禁止法 (4)
- 環境問題 (2)
- 知的財産権 (15)
- 税金関係 (5)
- 行政処分 (1)
- 裁判 (34)
- 証拠を集める (5)
- 遺産相続・遺言問題 (4)
- 顧客とのトラブル (13)
- 不動産に関するトラブル (2)
- 不動産業の法律相談 (67)
- 介護業界のトラブル (2)
- 仕事術・時間術 (68)
- 健康・セルフケア (27)
- 勉強法 (5)
- 営業 (4)
- 子育て (10)
- 建設業の法律相談 (332)
- 会社の株式のトラブル (1)
- 元請けや下請けのトラブル (10)
- 取引先とのトラブル (50)
- 契約書のトラブル (3)
- 社員との労働トラブル (263)
- 弁護士業界 (43)
- 情報発信 (134)
- SNS (3)
- Voicy(音声配信) (2)
- YouTube (9)
- セルフマガジン (1)
- ブログ (89)
- メルマガ (4)
- 棒人間 (3)
- 電子書籍(Kindleブック) (1)
- 料理 (2)
- 最近読んだ本 (20)
- 生き方 (59)
- 私(吉田悌一郎)ってどんな人? (34)
- 私の弁護士としてのスタンス (14)
- 酒こそわが人生 (19)
- 離島での弁護士活動 (4)
- 顧問契約 (24)
人気記事(トータル)
人気記事(月間)
月別記事
- 2026年2月 (26)
- 2026年1月 (31)
- 2025年12月 (31)
- 2025年11月 (30)
- 2025年10月 (31)
- 2025年9月 (30)
- 2025年8月 (31)
- 2025年7月 (31)
- 2025年6月 (30)
- 2025年5月 (31)
- 2025年4月 (30)
- 2025年3月 (31)
- 2025年2月 (28)
- 2025年1月 (33)
- 2024年12月 (31)
- 2024年11月 (30)
- 2024年10月 (31)
- 2024年9月 (30)
- 2024年8月 (31)
- 2024年7月 (31)
- 2024年6月 (30)
- 2024年5月 (31)
- 2024年4月 (30)
- 2024年3月 (31)
- 2024年2月 (29)
- 2024年1月 (31)
- 2023年12月 (31)
- 2023年11月 (30)
- 2023年10月 (31)
- 2023年9月 (30)
- 2023年8月 (31)
- 2023年7月 (31)
- 2023年6月 (30)
- 2023年5月 (31)
- 2023年4月 (30)
- 2023年3月 (31)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (31)
- 2022年12月 (31)
- 2022年11月 (31)
- 2022年10月 (39)
- 2022年9月 (4)
- 2022年1月 (1)

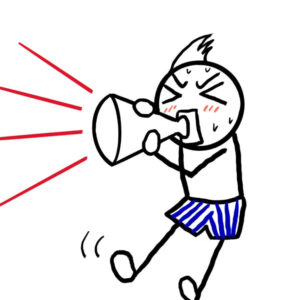

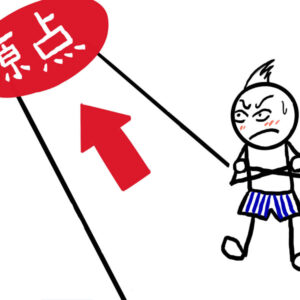
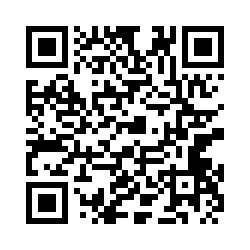













Profile
中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。