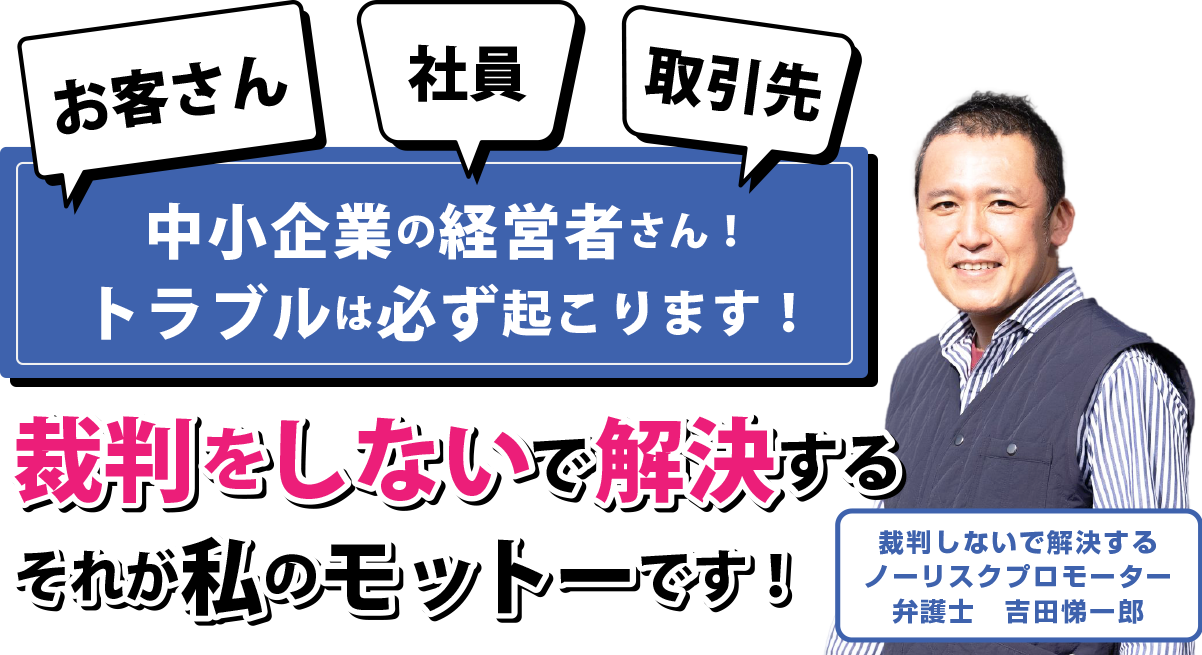
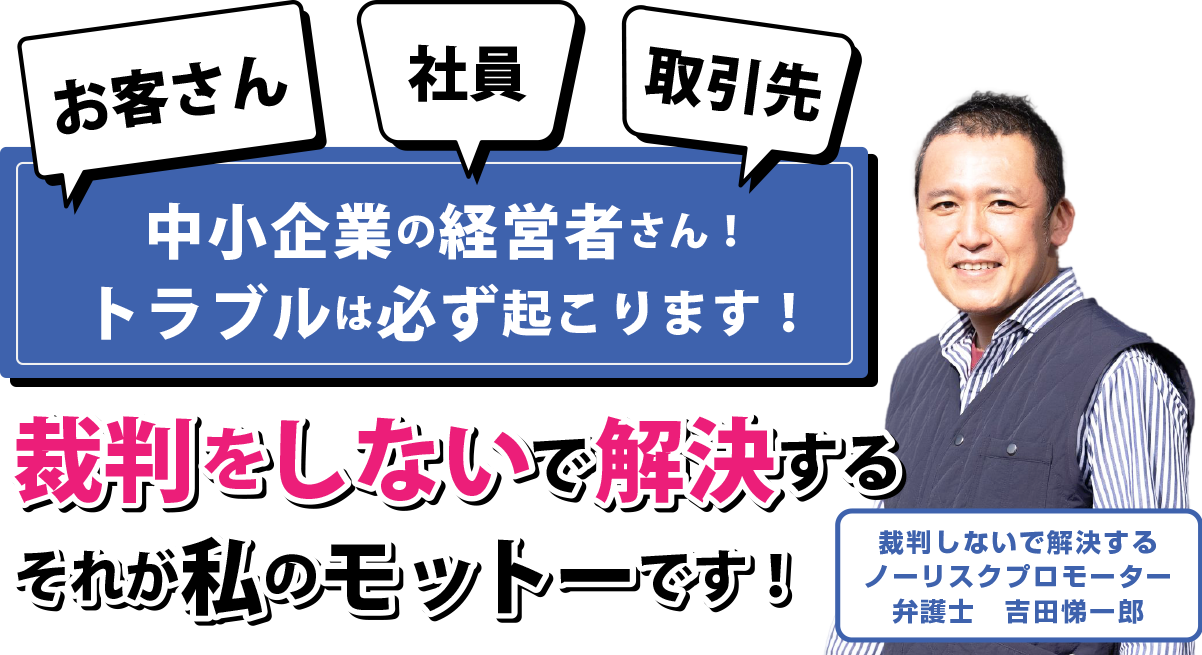
「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
初めての方はこちらのオススメ記事をお読みください一覧はこちら
「下請法」が変わる!2026年1月施行までに中小企業がすべき準備とは?
下請法が改正され
来年2026年1月から施行
されることになりました。
中小企業としても
このタイミングで改正法の概要を理解し
施行に備えた準備を行なっておく
必要があります。
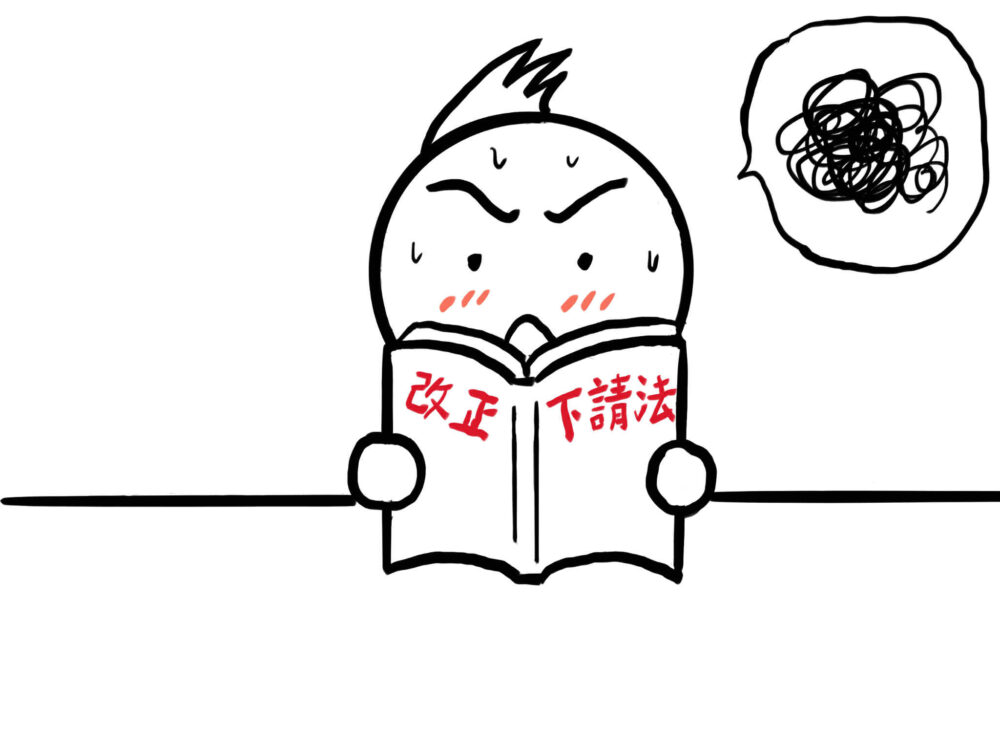
(今日の「棒人間」 下請法の改正に備える??)
<毎日更新1525日目>
法律の用語から大きく変わる?
改正下請法が
先の通常国会で成立しました。
この下請法の改正は約20年ぶりで
来年2026年1月1日から施行される予定です。
今回の改正の主な目的は
近年の急激な人件費
原材料費
エネルギーコストの上昇を背景に
中小企業が価格転嫁しやすい環境を整え
賃上げを後押しするためとされています。
この改正法では
そもそも「下請」という用語が
見直されることになりました。
それは
「下請」という言葉が
発注者と受注者が対等な
関係ではないという語感を与える。
時代の変化に伴い
「下請」という用語が使われなく
なっている実態があることが
理由とされています。
そこで
今の下請法の正式名称は
「下請代金支払遅延等防止法」と言いますが
改正法ではそれが
「製造委託等に係る中小受託事業者
に対する代金の支払の遅延等の
防止に関する法律」と変わります。
えらく長い名前の法律で
略称は「中小受託法」あるいは
「中小受託取引適正化法(取適法)」
になるようですね。
そして
改正法では
従来の用語が次のように
改められることになりました。
下請事業者→中小受託事業者
下請代金→製造委託等代金
いずれにしても
施行は来年1月ですから
多くの中小企業で今年中に法改正への
対応が必要となるということです。
主な改正ポイント
今回の法改正の主要な
ポイントは次の4つです。
価格交渉ルールの明文化
従来から
原材料費などのコストが
上昇しているにも関わらず
取引相手が値上げに応じてくれず
価格が据え置かれるという
「買いたたき」が問題となってきました。
「買いたたき」自体は
現行の下請法でも禁止されています。
今回の改正法ではさらに
こうした「買いたたき」行為
への対応策として
協議を適切に行わずに代金を
一方的に決定する行為が
新たな禁止行為として規定されました。
手形決済の禁止
さらに
改正法では
手形による支払いが禁止されました。
従来は
支払いサイトが長い
約束手形で支払うことで
受注者の資金繰りが悪化する
ことが問題とされてきました。
なお
そもそも政府が2026年中に
約束手形の利用の廃止を
目標として掲げています。
そして
主要銀行などでも同年中に手形の発行や
手形決済サービスを終了させる
方針を決めています。
新たに一定の運送委託が規制対象に追加
取引先に物品を納品するために
運送業者に委託する取引などは
従来は下請法の適用外とされていました。
しかし
こうした取引では
立場の弱い物流事業者が
契約にない荷役や荷待ちを無償で
行わされているという実態がありました。
そこで
改正法では
こうした取引も「特定運送委託」として
新たに規制の対象に追加されました。
従業員数を基準とした適用基準の追加
現行の下請法では
資本金の額などを基準にその
適用範囲が定められています。
一例を挙げれば
資本金3億円を超える法人が
資本金3億円以下の法人に製造委託
などを行う場合が適用対象とされています。
ただ
こうしたケースで
意図的に資本金を3億円以下に
設定するなどして
下請法の適用を意図的に
逃れるケースがありました。
会社法が改正されて
以前よりも資本金の減少の手続きを
やりやすくなったことも影響しています。
そこで
改正法では
新たに資本金の基準に加えて
従業員数を基準とした
適用基準を追加しました。
改正法施行までに準備しておきたいこと
さて
中小企業としては
今回の改正を踏まえて
約半年後に迫った施行までに
具体的にどのような準備を
しておけば良いのでしょうか?
まず
1点目は
取引先との価格交渉体制の
整備があげられます。
上記のように
改正法では
価格交渉のルールが
明文化されました。
そこで
こうした価格交渉に備えて
たとえば適正なコスト計算
(材料費、人件費、原価)に基づく
価格根拠資料の作成を行うべきでしょう。
そして
実際の取引先との交渉の経過などの
記録を残すための体制を整備
しておく必要があります。
次に
上記のとおり
手形取引ができなくなりますので
今現在も手形決済を行なっている会社は
取引先への支払方法の変更を
検討しなければなりません。
さらに
単価や代金額、納期、検収基準など
契約条件が曖昧な場合は
とかく取引先との間で
トラブルになりがちです。
そこで
やはり取引先との契約書を
もう1度見直し
整備しておく必要があります。
そして
改正法の内容を周知するため
社内で研修等を行う必要もあるでしょう。
交渉が現場任せになってしまっていると
知らず知らずのうちに法律違反を
犯してしまうリスクもあります。
いずれにしても
改正法はあと約半年で施行されます。
まだまだ先のように見えて
実はあまり時間はありません。
改正法が施行されて混乱に陥らないよう
早めの準備が大切だと考えます。
それでは
また。
◼️新作note(有料記事)「ファン付き作業着は義務?」知らなきゃ大損!夏の熱中症対策、会社がすべきこと
◾️裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール
◾️あなたの会社のトラブルを予防します〜あんしん法務ガード(顧問契約)
◼️「裁判沙汰」を予防する、契約書作成・リーガルチェックサービス
◾️【無料】セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付
◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)
最新動画
今回は、「下請けが全責任を負う契約を結んでいても、元請けが責任を負う理由」というテーマでお話ししています。
お問い合わせ

| 住所 | 150-0031 東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階 マップを見る |
|---|---|
| 受付時間 | 【平日】9:30〜18:00 【土曜日】9:30〜12:00 |
関連記事
カテゴリー
- キャンプ (5)
- このブログのコンセプト (23)
- セミナーのお知らせ (3)
- フリーランス保護法 (3)
- 一般的な法律相談 (363)
- AIと法律問題 (3)
- クレーマー・カスハラ対策 (48)
- ネットのトラブル (6)
- フリーランスの法律相談 (3)
- 下請法 (28)
- 不正競争防止法 (8)
- 事業承継問題 (16)
- 企業損害のトラブル (4)
- 会社法関係 (37)
- 個人情報保護法 (2)
- 倒産・債務整理 (2)
- 債権回収 (10)
- 内容証明 (3)
- 内部通報(公益通報) (3)
- 刑事関係 (4)
- 名誉・プライバシー・肖像権侵害 (2)
- 契約書 (42)
- 悪徳業者とのトラブル (7)
- 損害賠償 (3)
- 景品表示法 (11)
- 株主総会トラブル (10)
- 業務委託契約 (11)
- 法律相談を受ける (9)
- 独占禁止法 (4)
- 環境問題 (2)
- 知的財産権 (15)
- 税金関係 (5)
- 行政処分 (1)
- 裁判 (34)
- 証拠を集める (5)
- 遺産相続・遺言問題 (4)
- 顧客とのトラブル (13)
- 不動産に関するトラブル (2)
- 不動産業の法律相談 (67)
- 介護業界のトラブル (2)
- 仕事術・時間術 (68)
- 健康・セルフケア (27)
- 勉強法 (5)
- 営業 (4)
- 子育て (10)
- 建設業の法律相談 (332)
- 会社の株式のトラブル (1)
- 元請けや下請けのトラブル (10)
- 取引先とのトラブル (50)
- 契約書のトラブル (3)
- 社員との労働トラブル (263)
- 弁護士業界 (43)
- 情報発信 (134)
- SNS (3)
- Voicy(音声配信) (2)
- YouTube (9)
- セルフマガジン (1)
- ブログ (89)
- メルマガ (4)
- 棒人間 (3)
- 電子書籍(Kindleブック) (1)
- 料理 (2)
- 最近読んだ本 (20)
- 生き方 (59)
- 私(吉田悌一郎)ってどんな人? (34)
- 私の弁護士としてのスタンス (14)
- 酒こそわが人生 (19)
- 離島での弁護士活動 (4)
- 顧問契約 (24)
人気記事(トータル)
人気記事(月間)
月別記事
- 2026年2月 (26)
- 2026年1月 (31)
- 2025年12月 (31)
- 2025年11月 (30)
- 2025年10月 (31)
- 2025年9月 (30)
- 2025年8月 (31)
- 2025年7月 (31)
- 2025年6月 (30)
- 2025年5月 (31)
- 2025年4月 (30)
- 2025年3月 (31)
- 2025年2月 (28)
- 2025年1月 (33)
- 2024年12月 (31)
- 2024年11月 (30)
- 2024年10月 (31)
- 2024年9月 (30)
- 2024年8月 (31)
- 2024年7月 (31)
- 2024年6月 (30)
- 2024年5月 (31)
- 2024年4月 (30)
- 2024年3月 (31)
- 2024年2月 (29)
- 2024年1月 (31)
- 2023年12月 (31)
- 2023年11月 (30)
- 2023年10月 (31)
- 2023年9月 (30)
- 2023年8月 (31)
- 2023年7月 (31)
- 2023年6月 (30)
- 2023年5月 (31)
- 2023年4月 (30)
- 2023年3月 (31)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (31)
- 2022年12月 (31)
- 2022年11月 (31)
- 2022年10月 (39)
- 2022年9月 (4)
- 2022年1月 (1)

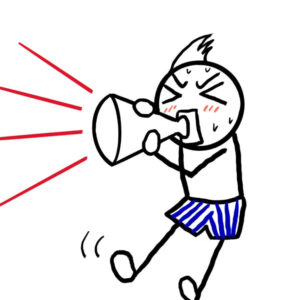

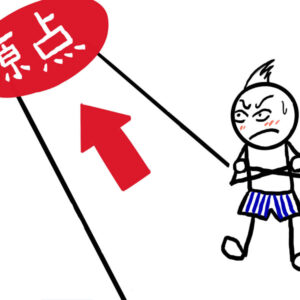
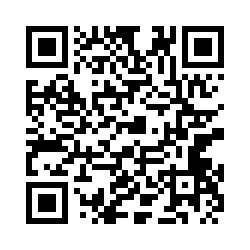













Profile
中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。