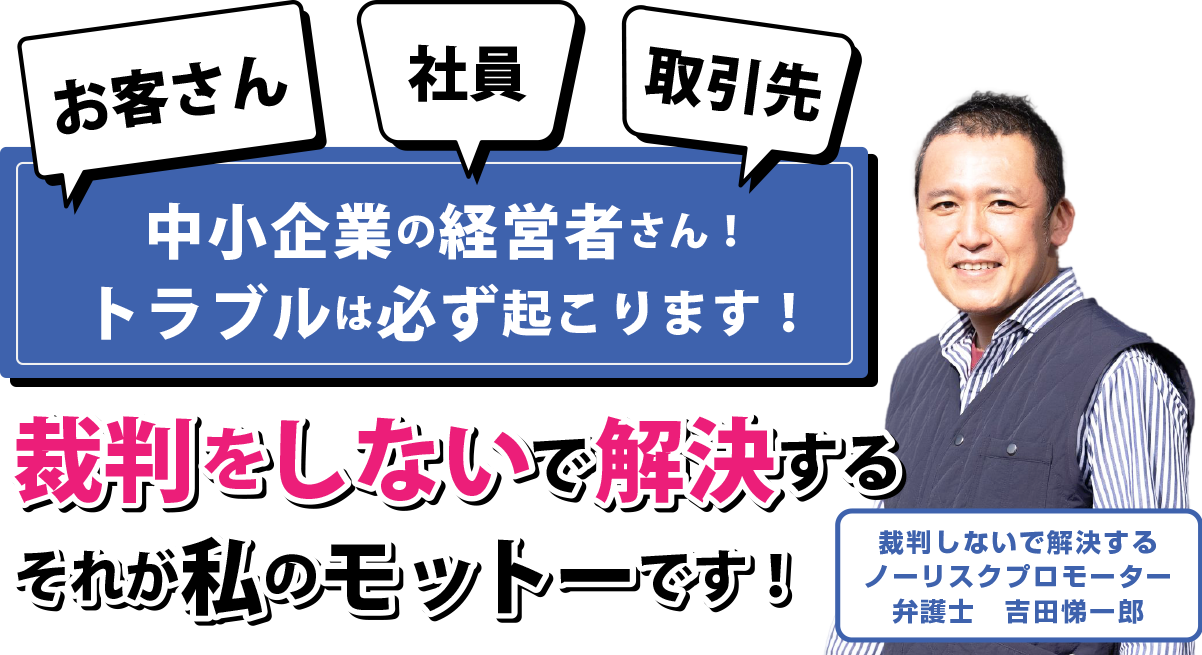
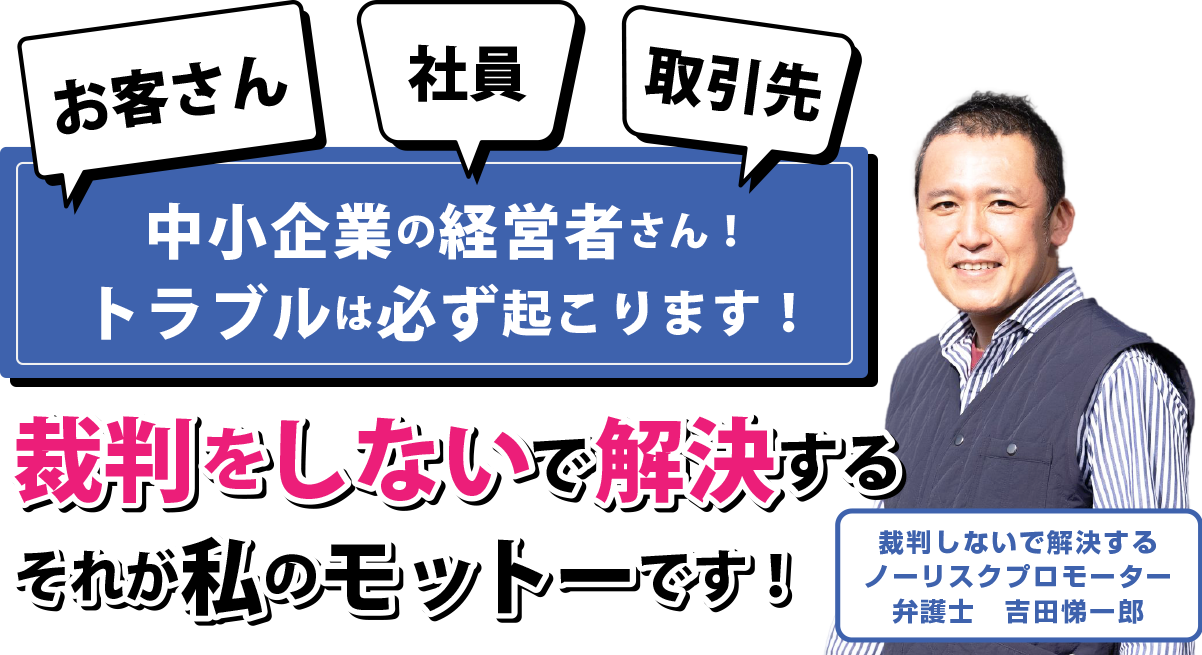
「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
初めての方はこちらのオススメ記事をお読みください一覧はこちら
建築工事が予定より遅れた…損害賠償はどうなる?過失相殺の仕組み
契約に違反すると
債務不履行といって
損害賠償責任が発生する
場合があります。
しかし
契約の相手方の方にも
落ち度があった場合
「過失相殺」といって賠償額が
その分減額されることがあります。

(今日の「棒人間」 痛み分け??)
<毎日更新1527日目>
契約書に定めた「工期」の意味

オタクの工事が契約書に書かれた「工期」に間に合わなかった!これは契約違反じゃないか!

いや、しかしそれはオタクがいろいろと・・・

うるさい!「工期」は契約書にきちんと書いてある。それに間に合わなかったんだからオタクの契約違反だ!損害賠償を請求する!
工務店が請け負う建築請負契約。
通常
契約書には建物の完成及び引渡が
行われる「工期」が定められます。
この契約書に書かれた「工期」には
いったいどのような意味が
あるのでしょうか?
契約というものは
当事者間でこういう約束をした
ということを意味しますので
基本的にその内容には
「拘束力」があります。
「拘束力」というのは
相手の承諾なしにその
約束を変更できない
ということです。
ですから
工務店側に落ち度があり
それによって「工期」に
間に合わなかったということになれば
それは工務店側の契約違反
ということになります。
契約違反というのは
法律上は「債務不履行」と言われます。
その場合
契約の当事者は
違反した相手方に対して損害賠償を
請求することができます。
損害賠償について契約書に
規定がある場合もありますが
仮にそうした規定がなくても
損害賠償請求は可能です。
すなわち
民法415条1項で
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
と規定されています。
「債務の本旨に従った履行をしない」
というのは
契約違反がその典型例で
工務店側の落ち度で「工期」に
間に合わなかった場合も
これにあたります。
「工期」に遅れたことの責任
ここで考えられる顧客の
「損害」というのは
例えば、新しい家の工期が
間に合わなかったため
その間ホテル住まいを
余儀なくされた場合の
宿泊費などが考えられます。
それでは
工務店の工事が「工期」に
間に合わなかった原因が
主に注文した顧客の側に
あった場合はどうなるのでしょうか?
たとえば
よくある例ですが
契約が成立し
工務店が着工した後になり
顧客の側で
契約書に記載のない様々な
仕様変更を求めてきたり
追加工事をいろいろと要求してきた。
工務店側でその顧客の
要求に従っていたため
当初の「工期」に間に合わなかった
ということがあり得ます。
そんな場合にまで
工務店側は上記の「債務不履行責任」を
負わなければならないのでしょうか?
過失相殺とは?
実は
このようなケースについても
民法に規定があります。
すなわち
民法418条では
債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
と規定されています。
これを
「過失相殺(かしつそうさい)」
と言います。
すなわち
工務店側の債務不履行
(上記の例では、工期に間に合わなかった)
等について
債権者(つまり
上記の例では発注者である顧客)に
過失があったときです。
このような場合には
本来工務店側が支払うべき
損害賠償の額から
顧客側の過失の割合に応じて
金額を減額することができる
という制度です。
まぁ
いわゆる「痛み分け」
といったところでしょうか?
このように
実際の取引社会のトラブル解決
には「バランス」が重要で
民法はまさに契約当事者の
バランスを図ることを狙っています。
つまり
原則として契約の違反があれば
それは違反した工務店に
まず責任を負わせる。
しかし
注文者(顧客)の側にも
債務不履行の発生の原因がある
というような場合には
顧客にも一定の負担を求める。
このようにして
発生した損害を契約当事者で
公平に分担するよう
バランスを図っている
というわけです。
ただ
この工務店としては
やはり顧客から仕様変更や
追加工事の依頼を受けた段階で
その時点における約束内容を
きちんと書面化しておくべきでした。
つまり
「合意書」とか「覚書」といった
形で構いませんので
新たな追加工事の内容や代金
それによって当初の「工期」の延長が
見込まれるのであればその旨を
きちんと記載しておくべきでした。
万が一トラブルが深刻化した場合には
民法は上記のようにある程度
バランスは図ってくれます。
しかし
いったん「裁判沙汰」になれば
当事者それぞれ大変な
負担を負うことになり
時間もかかります。
やはり
このブログでもお伝えしているとおり
トラブルや「裁判沙汰」を事前に
予防することが大切です。
そのためには
常日頃からそうした意識を持ち
工夫をすることにアンテナを
張っておきたいものですね。
それでは
また。
◼️新作note(有料記事)「ファン付き作業着は義務?」知らなきゃ大損!夏の熱中症対策、会社がすべきこと
◾️裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール
◾️あなたの会社のトラブルを予防します〜あんしん法務ガード(顧問契約)
◼️「裁判沙汰」を予防する、契約書作成・リーガルチェックサービス
◾️【無料】セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付
◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)
最新動画
今回は、「雇用の「最初の一歩」が肝心!社員採用時に必要な法的書類とは?」というテーマでお話ししています。
活動ダイジェスト
お問い合わせ

| 住所 | 150-0031 東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階 マップを見る |
|---|---|
| 受付時間 | 【平日】9:30〜18:00 【土曜日】9:30〜12:00 |
関連記事
カテゴリー
- キャンプ (5)
- このブログのコンセプト (23)
- セミナーのお知らせ (3)
- フリーランス保護法 (3)
- 一般的な法律相談 (363)
- AIと法律問題 (3)
- クレーマー・カスハラ対策 (48)
- ネットのトラブル (6)
- フリーランスの法律相談 (3)
- 下請法 (28)
- 不正競争防止法 (8)
- 事業承継問題 (16)
- 企業損害のトラブル (4)
- 会社法関係 (37)
- 個人情報保護法 (2)
- 倒産・債務整理 (2)
- 債権回収 (10)
- 内容証明 (3)
- 内部通報(公益通報) (3)
- 刑事関係 (4)
- 名誉・プライバシー・肖像権侵害 (2)
- 契約書 (42)
- 悪徳業者とのトラブル (7)
- 損害賠償 (3)
- 景品表示法 (11)
- 株主総会トラブル (10)
- 業務委託契約 (11)
- 法律相談を受ける (9)
- 独占禁止法 (4)
- 環境問題 (2)
- 知的財産権 (15)
- 税金関係 (5)
- 行政処分 (1)
- 裁判 (34)
- 証拠を集める (5)
- 遺産相続・遺言問題 (4)
- 顧客とのトラブル (13)
- 不動産に関するトラブル (2)
- 不動産業の法律相談 (67)
- 介護業界のトラブル (2)
- 仕事術・時間術 (68)
- 健康・セルフケア (27)
- 勉強法 (5)
- 営業 (4)
- 子育て (10)
- 建設業の法律相談 (332)
- 会社の株式のトラブル (1)
- 元請けや下請けのトラブル (10)
- 取引先とのトラブル (50)
- 契約書のトラブル (3)
- 社員との労働トラブル (263)
- 弁護士業界 (43)
- 情報発信 (134)
- SNS (3)
- Voicy(音声配信) (2)
- YouTube (9)
- セルフマガジン (1)
- ブログ (89)
- メルマガ (4)
- 棒人間 (3)
- 電子書籍(Kindleブック) (1)
- 料理 (2)
- 最近読んだ本 (20)
- 生き方 (59)
- 私(吉田悌一郎)ってどんな人? (34)
- 私の弁護士としてのスタンス (14)
- 酒こそわが人生 (19)
- 離島での弁護士活動 (4)
- 顧問契約 (24)
人気記事(トータル)
人気記事(月間)
月別記事
- 2026年2月 (26)
- 2026年1月 (31)
- 2025年12月 (31)
- 2025年11月 (30)
- 2025年10月 (31)
- 2025年9月 (30)
- 2025年8月 (31)
- 2025年7月 (31)
- 2025年6月 (30)
- 2025年5月 (31)
- 2025年4月 (30)
- 2025年3月 (31)
- 2025年2月 (28)
- 2025年1月 (33)
- 2024年12月 (31)
- 2024年11月 (30)
- 2024年10月 (31)
- 2024年9月 (30)
- 2024年8月 (31)
- 2024年7月 (31)
- 2024年6月 (30)
- 2024年5月 (31)
- 2024年4月 (30)
- 2024年3月 (31)
- 2024年2月 (29)
- 2024年1月 (31)
- 2023年12月 (31)
- 2023年11月 (30)
- 2023年10月 (31)
- 2023年9月 (30)
- 2023年8月 (31)
- 2023年7月 (31)
- 2023年6月 (30)
- 2023年5月 (31)
- 2023年4月 (30)
- 2023年3月 (31)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (31)
- 2022年12月 (31)
- 2022年11月 (31)
- 2022年10月 (39)
- 2022年9月 (4)
- 2022年1月 (1)

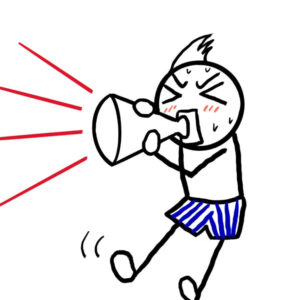

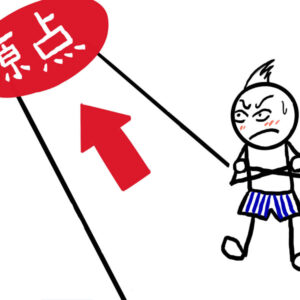
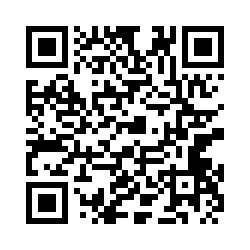













Profile
中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。