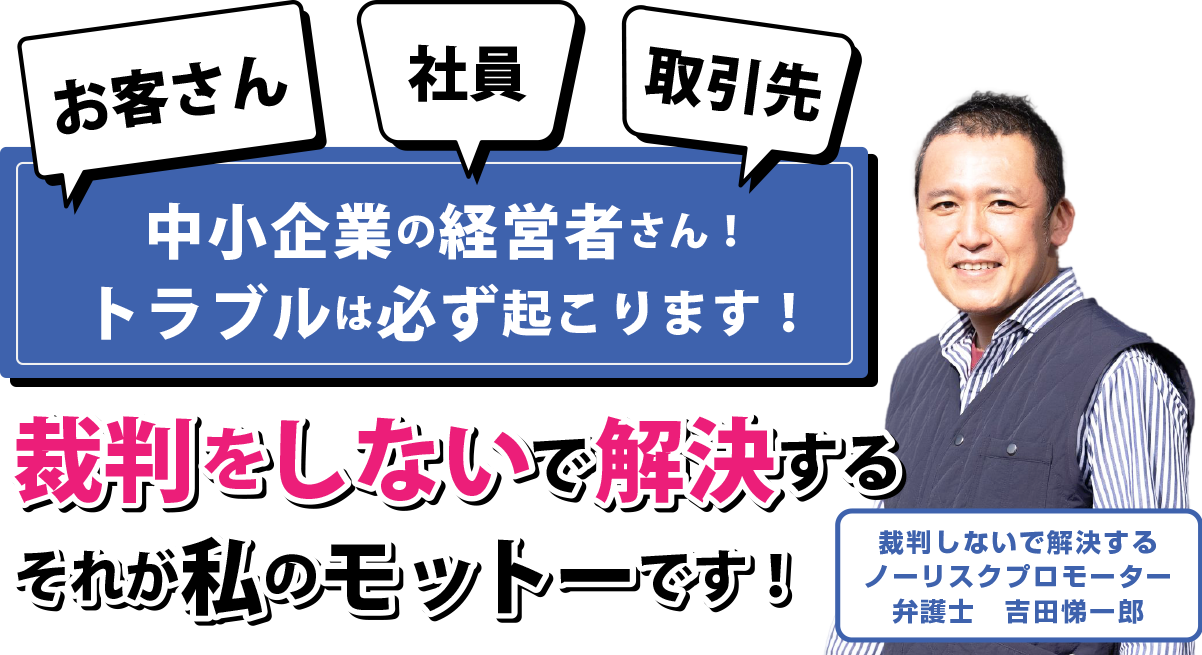
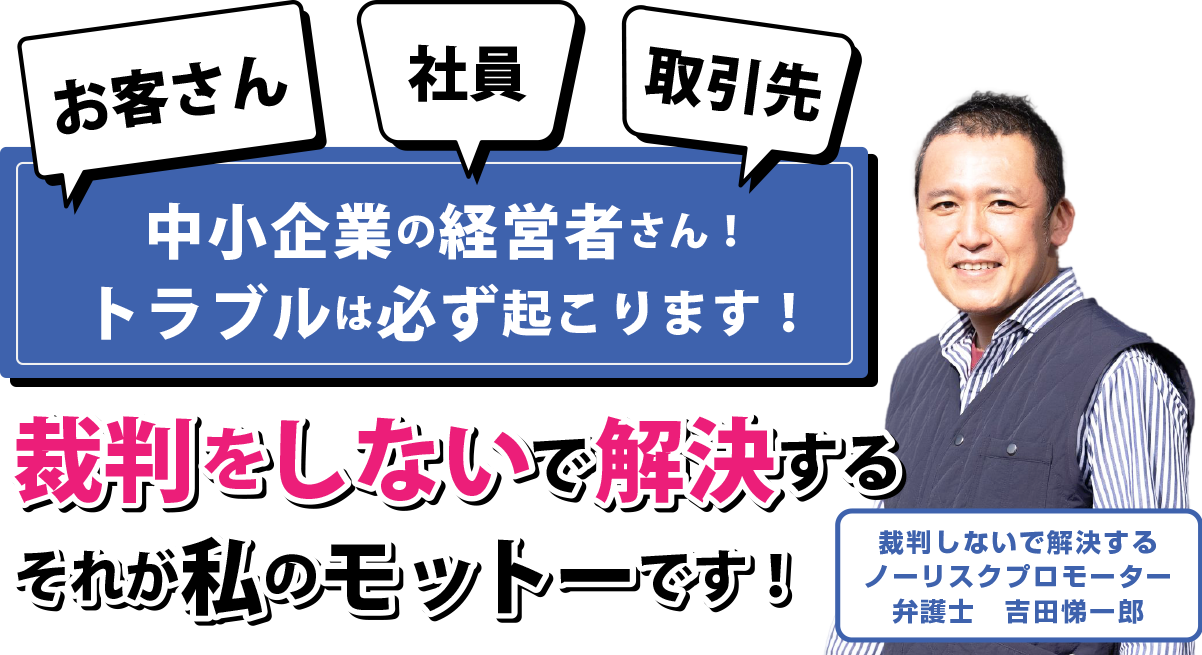
「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
初めての方はこちらのオススメ記事をお読みください一覧はこちら
【店舗の騒音】近隣住民からのクレームにどう対処すべきか?
飲食店を営んでいると、
近隣の住民から騒音が
うるさいというクレームを
受けることがあります。
こんなとき、
お店側としては
どのように対応したら
よいのでしょうか?

(今日の「棒人間」 騒音のクレームを言う人)
<毎日更新961日目>
近隣住民からの騒音のクレーム
忘年会シーズン真っ只中。
今年は、
コロナが明けた影響もあり、
しばらく控えていた忘年会を
復活させるという人も
多いでしょう。
先日、
都内で数店舗の飲食店を
営む会社の社長さんから
ご相談を受けました。
その会社の飲食店の
近隣住民から、
お店の騒音がうるさいので、
何とかしてほしい、
というクレームを
受けているそうです。
そのお店は、
お昼の12時から夜の
12時まで営業しており、
お昼はランチ、
夜はお酒の提供もある
居酒屋として営業
しています。
お昼の時間はともかく、
夜の時間帯になると、
お客さんがお店でお酒を
飲んで盛り上がることも
多くなります。
お酒を飲むと、
どうしても声が大きく
なる人も出てくるし、
騒がしくもなるでしょう。
夜10時以降の時間帯に
騒音があると、
子どもやお年寄りが
寝れないとか、
そういったクレームが
あるようです。
社長としても、
対処の仕方がわからず、
なんとなくやり過ごしていたら、
だんだん近隣の住民からの
クレームは激しくなってきます。
中には、

と言ってくる人もいて、
参っているとのことです。
どのような法的責任を負うか?
この点、
飲食店が、
騒音の問題でどのような
法的な責任を負う
可能性があるのか、
見てみたいと思います。
まず、
騒音規制法という法律で、
飲食店営業等における
深夜の騒音については、
必要があれば各地方自治体の
条例などで規制される
ことになっています。
深夜営業というのは、
一般に午後10時から
午前5時までの時間帯を
さします。
また、
大規模小売店舗立地法や、
風営法でも、
店舗の騒音を規制する
規定が置かれています。
こうした行政規制に
違反している場合には、
法律や条例に基づく
指導や改善勧告、
営業停止命令などを
受ける可能性があります。
また、
仮にこうした規制に
違反していない場合でも、
一定の騒音が近隣住民に
対する不法行為になる
場合もあります。
それはどういう場合か
というと、
その騒音が周辺住民が
社会生活上受忍すべき範囲
を超えていると評価
される場合です。
この社会生活上受忍すべき範囲を
「受忍限度」と言います。
「受任限度」を
超えている場合には、
近隣住民に対する
損害賠償を行う必要が
出てきます。
この「受忍限度」を
超えているか否か
については、
①被害の程度、②加害行為の公共性、③加害行為の規制基準違反の有無、④損害防止対策の有無、⑤加害者と被害者のどちらが先に住んでいたかや周辺の事情(地域性)
などを考慮して
判断されることに
なっています。
こうした受忍限度を
超えているという事実は
基本的に住民の側で
証明しなければならない
ことになっています。
ですから、
実際の裁判で騒音が
受忍限度を超えると
判断されることは
多くはありません。
したがって、
仮に周辺住民から
裁判を起こす、
などと言われても、
会社側はあくまで
落ち着いて冷静に
対応することが大切です。
クレームへの対処法
ただし、
いくら法的な責任が
認められる可能性が
低いとはいえ、
周辺住民の声を
まったく無視して
お店を営業し続けるのは、
得策ではありません。
その地域でお店を
営業していくためには、
やはり近隣住民との良好な
関係は不可欠です。
ですから、
まずクレームにはきちんと
真摯に耳を傾ける必要が
あるでしょう。
その上で、
お店の方でできる対策、
たとえば防音設備を
店内に設置するとか、
お店の営業時間の
短縮を検討するなど、
実施可能な騒音防止対策を
検討する必要は
あると考えます。
近隣住民との
「裁判沙汰」を避けるためにも、
仮に法的な責任がない場合でも、
誠実な対応は求められると
思います。
それにしても、
社会で生活をしていれば、
騒音に限らず
いろいろと我慢しなければ
ならないことも
少なくないでしょう。
どの程度までが
我慢すべき範囲で、
どこからがそれを
超えているか、
これを丁寧に考える
必要があるでしょうね。
それでは、
また。
◾️裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール
◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)
最新動画
今回は、社員とのトラブル予防、雇用契約書を作った方がよい3つの理由、というテーマでお話ししています。
活動ダイジェスト
新規のお客様の法律相談や、オンラインでの裁判期日などでした。
夕方は、早めに帰宅して息子の習い事(美術教室)の送迎、合間にブログ、夕食作りなどでした。
お問い合わせ

| 住所 | 150-0031 東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階 マップを見る |
|---|---|
| 受付時間 | 【平日】9:30〜18:00 【土曜日】9:30〜12:00 |
関連記事
カテゴリー
- キャンプ (5)
- このブログのコンセプト (23)
- セミナーのお知らせ (3)
- フリーランス保護法 (3)
- 一般的な法律相談 (361)
- AIと法律問題 (3)
- クレーマー・カスハラ対策 (48)
- ネットのトラブル (6)
- フリーランスの法律相談 (3)
- 下請法 (28)
- 不正競争防止法 (8)
- 事業承継問題 (16)
- 企業損害のトラブル (4)
- 会社法関係 (37)
- 個人情報保護法 (2)
- 倒産・債務整理 (2)
- 債権回収 (10)
- 内容証明 (3)
- 内部通報(公益通報) (3)
- 刑事関係 (4)
- 名誉・プライバシー・肖像権侵害 (2)
- 契約書 (41)
- 悪徳業者とのトラブル (6)
- 損害賠償 (3)
- 景品表示法 (11)
- 株主総会トラブル (10)
- 業務委託契約 (11)
- 法律相談を受ける (9)
- 独占禁止法 (4)
- 環境問題 (2)
- 知的財産権 (15)
- 税金関係 (5)
- 行政処分 (1)
- 裁判 (34)
- 証拠を集める (5)
- 遺産相続・遺言問題 (4)
- 顧客とのトラブル (13)
- 不動産に関するトラブル (2)
- 不動産業の法律相談 (67)
- 介護業界のトラブル (2)
- 仕事術・時間術 (68)
- 健康・セルフケア (27)
- 勉強法 (5)
- 営業 (4)
- 子育て (10)
- 建設業の法律相談 (328)
- 会社の株式のトラブル (1)
- 元請けや下請けのトラブル (10)
- 取引先とのトラブル (50)
- 契約書のトラブル (3)
- 社員との労働トラブル (259)
- 弁護士業界 (42)
- 情報発信 (134)
- SNS (3)
- Voicy(音声配信) (2)
- YouTube (9)
- セルフマガジン (1)
- ブログ (89)
- メルマガ (4)
- 棒人間 (3)
- 電子書籍(Kindleブック) (1)
- 料理 (2)
- 最近読んだ本 (20)
- 生き方 (57)
- 私(吉田悌一郎)ってどんな人? (34)
- 私の弁護士としてのスタンス (14)
- 酒こそわが人生 (19)
- 離島での弁護士活動 (4)
- 顧問契約 (24)
人気記事(トータル)
人気記事(月間)
月別記事
- 2026年2月 (17)
- 2026年1月 (31)
- 2025年12月 (31)
- 2025年11月 (30)
- 2025年10月 (31)
- 2025年9月 (30)
- 2025年8月 (31)
- 2025年7月 (31)
- 2025年6月 (30)
- 2025年5月 (31)
- 2025年4月 (30)
- 2025年3月 (31)
- 2025年2月 (28)
- 2025年1月 (33)
- 2024年12月 (31)
- 2024年11月 (30)
- 2024年10月 (31)
- 2024年9月 (30)
- 2024年8月 (31)
- 2024年7月 (31)
- 2024年6月 (30)
- 2024年5月 (31)
- 2024年4月 (30)
- 2024年3月 (31)
- 2024年2月 (29)
- 2024年1月 (31)
- 2023年12月 (31)
- 2023年11月 (30)
- 2023年10月 (31)
- 2023年9月 (30)
- 2023年8月 (31)
- 2023年7月 (31)
- 2023年6月 (30)
- 2023年5月 (31)
- 2023年4月 (30)
- 2023年3月 (31)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (31)
- 2022年12月 (31)
- 2022年11月 (31)
- 2022年10月 (39)
- 2022年9月 (4)
- 2022年1月 (1)

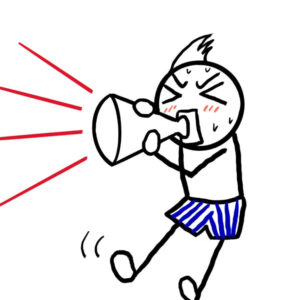

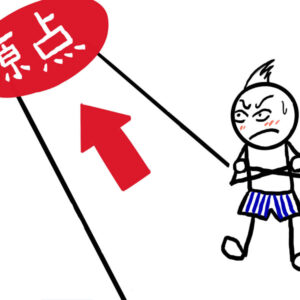
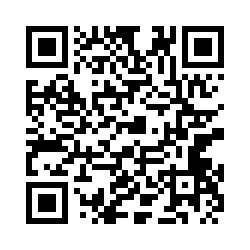













Profile
中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。